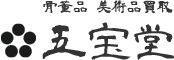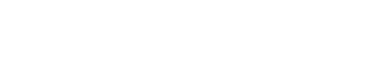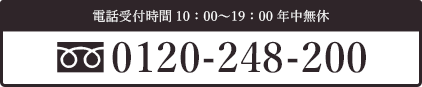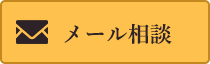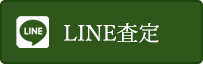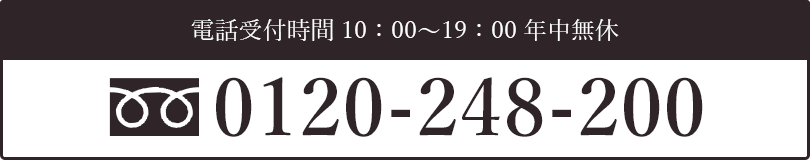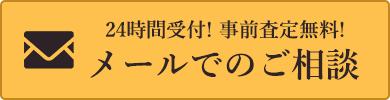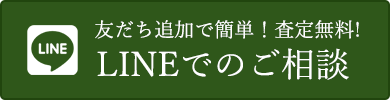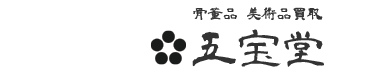| 作家名 | 北大路魯山人 |
|---|---|
| 作品名 | 赤呉須 湯呑 |
| 買取品目 | 茶道具 |
| 買取方法 | 出張買取 |
| ご依頼地域 | 東京都渋谷区 |
買取参考価格
100,000円
※買い取り価格は当日の価格であり、その価格を保証するものではありませんので予め御了承下さい。
五宝堂スタッフより
【北大路魯山人 (きたおうじ ろさんじん)について】
生没: 1883(明治16)年~1959(昭和34)年
北大路魯山人は京都府出身で明治後半から昭和時代に篆刻家、書道家、美食家、料理家、陶芸家、漆芸家、篆刻家など様々な分野で活躍しました。
陶芸家としては織部焼の重要無形文化候補としてあがりましたが断っています。本人は「作家」としてあがめた奉られるのを嫌っていた為だと言われています。徳に食事に合い「使える」器作りを信条とし、陶芸作品は魯山人自身が料理家であり美食家でもあった事から「用の美」を追求したものが多く存在しています。
その作品数は実に20万点以上、絵画、書、篆刻は1万点以上を産みだしたと言われていますが「作家」としての活動を嫌っていた事から落款、サインや署名等がない作品も多数存在しています。
【魯山人作品の査定ポイント】
北大路魯山人の作品は、日本国内での陶芸作家の中でも、特に高い評価を受けている一人です。
皿、ぐい呑、徳利、茶碗、花器などの種類、また他にも年代、意匠、状態、箱等の様々な要因によって買取相場価格は大きく違います。
作品の底部に掻銘、描銘、印銘で「ロ」「魯」「魯山人」等のサインがあります。
陶芸作品では、『箱』の有無が重要な査定ポイントになります。
共箱とは作家本人が署名をした箱で、識箱とは鑑定人や親族が箱書きしたものとなります。
共箱の方が、識箱よりも価値は高いです。魯山人作品は黒田陶苑の識箱に入っている場合が多く見受けられます。
北大路魯山人の作品は人気があるので贋物が多く存在します。
共箱や黒田陶々庵の鑑定箱があるからと言って安心はできません。
鑑定書や鑑定箱があっても再鑑定の必要性がある場合もあります。
その判断にはどうしても専門知識が必要となりますので、五宝堂ではまずは直接お品物を拝見させて頂き判断させて頂きます。
【略歴】
1883年 京都府愛宕郡上賀茂村(現在の京都市北区)にある上賀茂神社の社家の家に生まれる
1889年 木版師・福田武造の養子になる
1893年 丁稚奉公で京都の烏丸二条にでる。この時期に、京都画壇総師『竹内栖鳳』の作品に出合う
1896年 奉公から戻り養父の仕事を手伝いながら、扁額や篆刻の技術を身につける
1904年 日本美術協会開催の美術展覧会に『千字文』を出品し見事、褒状一等二席を受賞
1905年 洋画家『岡本太郎』の祖父である書画・岡本可亭の内弟子になる
1913年 素封家・河路豊吉に招かれ、この時代に小蘭亭の天井画や襖絵、篆刻など代表作となる傑作を残している
1916年 北大路魯山人の号を使い始める
1917年 便利堂を経営する中村竹四郎と出会い、古美術店「太雅堂」を共同経営する
1925年 料亭「星岡茶寮」を開店し、自身が創作した食器に料理を盛ってだしていた
1927年 美濃焼の代表作家『荒川豊蔵』を招き、鎌倉市山崎で『魯山人窯芸研究所・星岡窯』を設立
1946年 自身が創作した作品を直売する『火土火土美房』を開店
1954年 欧米で開催された展覧会で、『パブロ・ピカソ』『マルク・シャガール』と出会い親交を深めた
1955年 織部焼の人間国宝に指名されるも辞退した
1959年 肝硬変を患いこの世を去った
五宝堂では骨董品・美術品を中心に幅広いお買取品種を取り扱っておりますので、
経験と知識が豊富な査定士の確かな目利きで価値ある品を見極め、ご評価致します。
作家が不明なお品や価値があるか分からないお品でも、査定は無料でございますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。