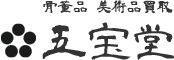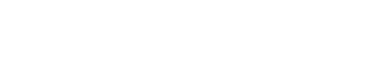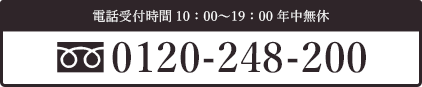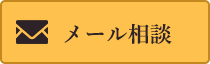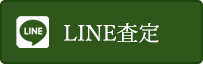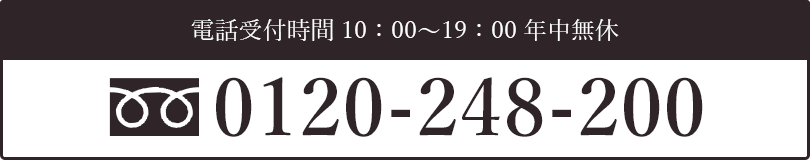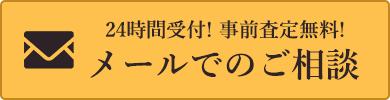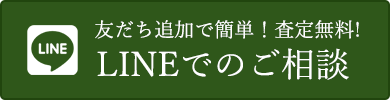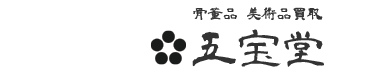| 作家名 | |
|---|---|
| 作品名 | 江戸時代 早乙女派四代 在銘 常州住早乙女家貞 鉄地六十二間筋兜 |
| 買取品目 | 武具・甲冑 |
| 買取方法 | 出張買取 |
| ご依頼地域 | 宮城県仙台市 |
買取参考価格
380,000円
※買い取り価格は当日の価格であり、その価格を保証するものではありませんので予め御了承下さい。
五宝堂スタッフより
【甲冑師の主な流派について】
現在、甲冑師の主な流派として知られているのは「春田派」・「明珍派」(みょうちんは)・「早乙女派」(さおとめは)・「岩井派」・「雪下派」(ゆきのしたは)です。
これら5派は「御家流」と称され、江戸時代に「徳川家康」をはじめとした大名らに召し抱えられ、「御抱具足師」(おかかえぐそくし)となっています。そうして仕えた藩主の好みや、地方的特色を取り入れながら甲冑(鎧兜)の制作は代々受け継がれていきました。
【早乙女派について】
早乙女派の始祖である「信康」は、明珍派・信家の弟子であると言われた人物です。また早乙女派の甲冑師は常陸国(現在の茨城県)出身が多いことから、在銘品には「常州住」([常州]は常陸国の別称)と切る作品がよく残っています。しかし常陸国以外の銘を切った国名はなく、また年紀を切った作品が少ない派閥でもありました。
早乙女派で在銘の多い甲冑師は、「家忠」・「家成」・「家貞」・「家親」です。
【兜の査定ポイント】
日本の兜は、武家政権の誕生した鎌倉時代に大きく発展したといわれ、鎌倉中期頃には政情の安定化もあり甲冑も華やかさが増しました。兜鉢とともに天辺の座や立物の彫り金物も精巧につくられ、兜の前立物は大きさを増していきます。その後、室町時代、戦国・安土桃山時代、江戸時代を経てさまざまなバリエーションが生まれます。とくに戦国・安土桃山時代には、武将の威厳を示すための「変り兜」が数多く登場しました。現在では、前立物だけでも龍、獅子、日、月、扇など種類は豊富です。
【兜の査定ポイント】
日本の兜は、武家政権の誕生した鎌倉時代に大きく発展したといわれ、鎌倉中期頃には政情の安定化もあり甲冑も華やかさが増しました。兜鉢とともに天辺の座や立物の彫り金物も精巧につくられ、兜の前立物は大きさを増していきます。その後、室町時代、戦国・安土桃山時代、江戸時代を経てさまざまなバリエーションが生まれます。とくに戦国・安土桃山時代には、武将の威厳を示すための「変り兜」が数多く登場しました。現在では、前立物だけでも龍、獅子、日、月、扇など種類は豊富です。
兜の買取でとくに重要となる査定ポイントは、製作年代、甲冑師(兜の製作者)、保管用の箱、保存状態が良いかどうかになります。
製作年代が分かれば、その当時どれくらい兜の生産が盛んであったかが見えてくるためです。
兜の生産量自体が少ない時代の作品であれば、自然と希少性は高まります。
大量生産された時期のものであれば、有名な武将や大名の愛用品かどうか検討する足がかりになります。
兜の価値を考えるとき、製作年代は大きな意味を持つのです。
有名甲冑師によって製作されたかどうかも重要な査定ポイントになります。
代表例を挙げると、鎌倉時代は熊野打、室町時代では春田派に雑賀派、戦国時代以降になると岩井派・明珍派・早乙女派とさまざまな流派が派生していきました。また、甲冑師が名前を入れるようになったのは室町時代の末期からと言われております。
また、甲冑師が誰であるか確認できるものが、兜を入れる箱です。一般的に保管専用の箱やケースであれば、甲冑師の名前を示す「兜の銘」が記載されています。銘が箱にしっかり記されていると高評価につながるため、兜の買取では箱の状態も大切なポイントのひとつです。
査定を依頼する際に最も重要なのは、「誰に見てもらうか」です。
一般的なリサイクルショップでは、時代甲冑など、様々な種類がある兜、鎧を正確に評価することは困難です。
選ぶべきは、骨董・美術品を専門に扱う業者です。
これらの業者は、市場動向や真贋を見分けるノウハウを持っています。
特に「甲冑の取り扱い実績」があるかどうかは、信頼性を測るひとつの指標になります。
五宝堂では骨董品・古美術品を中心に幅広いお買取品種を取り扱っております。
経験と知識が豊富な査定士の確かな目利きで価値ある品を見極め、ご評価致します。
作家が不明なお品や価値があるか分からないお品でも、査定は無料でございますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。